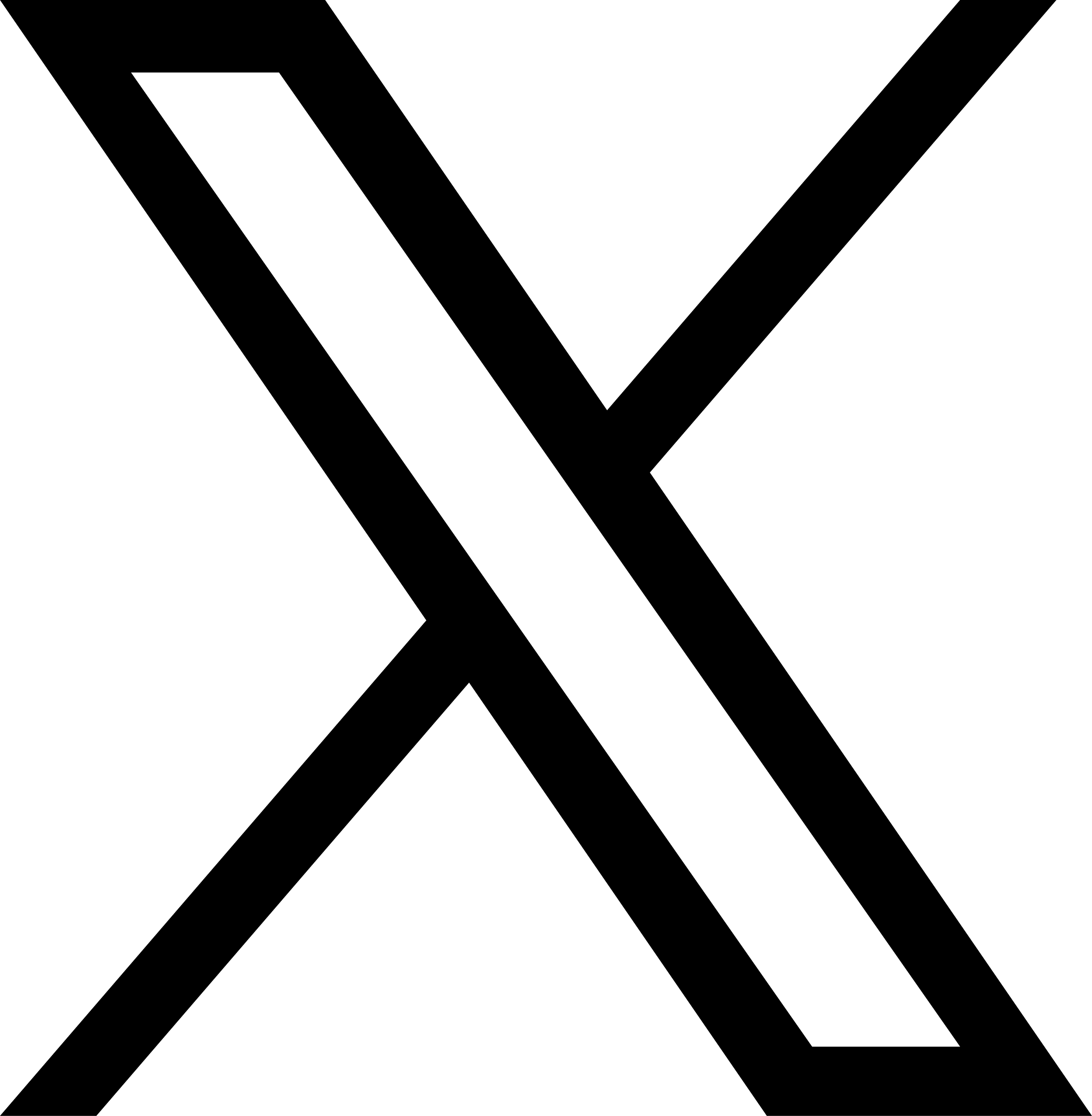タバコポイ捨て対策の成功例にはどのようなものがある?
2025.09.01

さまざまな施設の管理者が頭を悩ませているのが、「タバコポイ捨て」です。
そのまま放置することはできないので、対策を考えてはいるものの、上手くいかずに困っているというケースも多いでしょう。
今回のコラムでは、「タバコポイ捨て対策の成功例」について解説します。
タバコポイ捨て対策を行わないと火災やトラブルのリスクが上昇する
タバコポイ捨て対策の成功例について考える前に、どうして対策が必要になるのか、について考えてみましょう。
対策が必要な理由としては、次のようなものがあります。
火災の危険性が高まる
タバコポイ捨ての対策を行わなかった場合、最も危険なのが火災リスクの上昇です。
火のついたタバコの吸い殻をポイ捨てすると、そこから火災が発生して、最悪の場合には、人命が奪われてしまう可能性があります。
実際にタバコの吸い殻のポイ捨てが原因と見られる火災が、全国で発生しているのです。
環境汚染のリスク
また、タバコの吸い殻については、火災の危険性があるだけではありません。
環境汚染のリスクがあるということも理解しておかなければならないのです。
皆さんもご存知のように、タバコの吸い殻には、さまざまな有害物質が含まれています。
その有害物質が流れ出し、水や土などを汚染するとされているのです。
おそらく、多くの人は、タバコのポイ捨てと聞くと、それほど大きな問題ではないと考えてしまうでしょうが、実際には環境汚染につながるリスクがあるということを理解しておきましょう。
清掃に手間や時間、コストがかかる
タバコの吸い殻のポイ捨ては、火災のリスクや環境汚染のリスクがあると解説しました。
これだけでも、しっかりとした対策が必要であると理解してもらえたと思いますが、その他にも問題があるのです。
対策を行わなかった場合の問題として挙げられるのが、清掃に手間や時間、コストがかかるということ。
吸い殻をポイ捨てされてしまった場合には、当然清掃しなければならなくなるでしょう。
場所によっては、ボランティアの方や地域の方などが清掃をしてくれる場合もありますが、ポイ捨てされた吸い殻を片付けるのは、とても大変です。
手間がかかりますし、量が多い、あるいは捨てられているのが広範囲にわたるなどの場合には、清掃に時間もかかります。
さらに、回収した吸い殻を廃棄する場合には、費用がかかる場合もあるでしょう。
クレームの増加や近隣住民との関係悪化のリスク
その他で起こる可能性がある問題としては、隣接する施設や近隣住民、利用者などからのクレームの増加です。
タバコの吸い殻がポイ捨てされている状態を見ると、その施設を管理する管理者にクレームを入れる可能性が高まります。
クレームに対応するため、時間や人を割かなければいけなくなるでしょう。
それから、クレームが増加するというだけでなく、近隣施設の関係者や近隣住民との関係が悪化してしまう可能性もあります。
ここに挙げたように、タバコの吸い殻のポイ捨てに対して、十分な対策を行わないと、さまざまな問題が出て、深刻な状況になってしまう可能性があるのです。
だからこそ、放置するのではなく、しっかりとした対策を行いましょう。
イベント開催時など人が多く集まるときには注意が必要
最初に、どうしてタバコポイ捨て対策が必要なのか、について解説しました。
そのため、対策が必要な理由が理解できたと思いますが、次に頭に入れておかなければならないのが、どのようなときに、ポイ捨てが起こりやすくなるのか、ということです。
どのようなときに起こりやすくなるのか、について理解しておけば、対策もしやすくなるでしょう。
具体的には、次のような場合に、ポイ捨てが起こりやすくなります。
イベント開催時
最も注意が必要となるのが、イベント開催時です。
花火大会や音楽イベント、スポーツイベントなどのイベント開催時になります。
イベント開催時には、多くの人が集まるため、吸い殻のポイ捨てが起こる可能性が高くなるのです。
イベント開催時は、通常その施設を利用しない人も利用することになりますので、喫煙ルールを理解してない、喫煙可能な場所を把握してないこともあります。
また、管理者の中には、すでに喫煙スペースを設置しているため、大丈夫と十分な対策を行わない人もいるようです。
ですが、イベント開催時には多くの人が訪れることになりますので、喫煙スペースを設置していたとしても、スペースが足りなくなってしまうおそれがあります。
喫煙スペースを利用できなかった喫煙者が、喫煙を認められていない場所で勝手に喫煙する、吸い殻をポイ捨てする、可能性があるのです。
喫煙スペースを設置している場合でも、スペースが十分足りているか、などをしっかりと確認しておきましょう。
喫煙スペースを設置していたが撤去した場合
ポイ捨てが最も起こりやすいのは、イベント開催時ですが、その他にも起こりやすいときがあります。
それは、これまで喫煙スペースを設置していたものの、撤去した場合です。
現在では、健康経営に取り組む企業が増えています。
そのため、これまでは喫煙可能な場所での喫煙を認めていたものの、敷地内全面禁煙を実施することにした企業もあるのです。
喫煙スペースがあれば、灰皿に吸い殻を捨てればよかったのですが、それが撤去されてしまったとなると、吸い殻を捨てる場所がなくなってしまいます。
捨てる場所がなくなった喫煙者は、これまでの習慣を変えることができずに、そのまま前に灰皿が置かれていた場所に捨てる、あるいはその周囲に捨てるなどの行為を行う可能性があるのです。
イベント開催時には喫煙スペースを臨時で増やす
すでに解説しているように、イベント開催時には喫煙スペースを設置していても、足りなくなってしまうおそれがあります。
では、どのような対策を行えばよいのでしょうか?
イベント開催時における対策としては、臨時で喫煙スペースを増やすのがおすすめです。
喫煙スペースには、さまざまなタイプのものがあるので、イベント開催時のみ設置して置ける、工事不要な仮設タイプがおすすめ。
仮設タイプには、テント型タイプや移動式パーテーションタイプなどがあります。
仮設タイプは、工事不要ですし、基本的には置きたい場所に置けるので、非常に便利です。
イベント開催で、一時的に喫煙者が増えると予測できる場合には、対策として仮設タイプの喫煙スペースの設置を検討してみましょう。
タバコポイ捨て対策の成功例について
施設の管理者の方の中には、これまで対策を行ってきたが、上手くいかなかった、という人もいるでしょう。
それでは、タバコポイ捨て対策の成功例には、どのようなものがあるのか気になりませんか?
成功例には、次のようなものがあります。
投票型喫煙所
タバコポイ捨て対策の成功例として挙げられるのが、「投票型喫煙所」です。
この投票型喫煙所とは、その名称からも想像することができるように、二者択一の設問が用意されている灰皿で、自分で好きな方の答えを選んで、そちらに吸い殻を使って投票を行うというものになります。
一般的な喫煙所と大きく異なるのは、喫煙者が投票という形で楽しみながら、吸い殻を捨てられることです。
この投票型喫煙所を設置したところ、ポイ捨て数が90%減少したところもあると報告されています。
(参考:株式会社コソド 『ASK THE TOBACCO』)
タバコポイ捨て対策として、何をすればよいのかわからないという場合には、喫煙者も楽しむことができる、こちらの例を参考にしてみるのもよいでしょう。
ポスターの掲示と指導員によるパトロールの実施
投票型喫煙所以外の成功例としては、ポスターの掲示や指導員によるパトロールの実施があります。
ポスターの掲示では、吸い殻のポイ捨て禁止だけでなく、歩きタバコに関するポスターを作成・掲示。
住民などから苦情や相談があった場所にポスターを掲示する、希望者に配布を行うなどを実施。
それから、指導員によるパトロールを行い、歩きタバコや吸い殻のポイ捨てに関する巡回・指導を行ったそうです。
また、指導員にはポイ捨て禁止と書かれているビブスを着てもらい、朝・夕の毎日巡回を行うことで対策としています。
さらに、工夫されているのが、日本語だけの表記にするのではなく、英語やイラストも活用して表記を行っており、日本人だけでなく、外国人観光客にもわかりやすく、理解できるようにしているそうです。
日本語だけの表記だと、日本人には理解できますが、外国人は理解することができません。
ですから、英語やイラストを活用するのは、とてもよいアイデアと言えます。
具体的な数値が書かれていないため、どの程度の効果があったのか、についてはわかりません。
しかし、ポスターを掲示することで啓発を行い、指導員がパトロールを行い、注意や指導を行ったことで、改善が見られたと報告されています。
(参考 環境省 観光地におけるごみのポイ捨て・発生抑制対策実績と改善の事例集)
タバコポイ捨て対策における課題
さきほどは、タバコポイ捨て対策の具体的な成功例について紹介しました。
そのため、これから対策として取り入れようと考える人も多いでしょう。
もちろん、有効な対策と言えるのですが、課題もあります。
この課題についてもしっかりと理解しておく必要があるのです。
効果が期待できるのは限定的となってしまう場合がある
大きな課題として挙げられるのが、効果が期待できるのが限定的となってしまう場合があるということです。
すでに解説したように、成功例の1つには、投票型喫煙所があります。
たしかに、設置している周辺は利用してもらえる可能性が高いので、効果を期待することができるでしょう。
しかし、投票型喫煙所から距離が離れれば離れるほど、効果を期待できなくなってしまいます。
設置されている周辺であれば、喫煙者が興味を持って利用してくれるでしょうが、離れた場所では再びポイ捨てされてしまう可能性があるのです。
ですから、どうしても効果が限定的になってしまうという課題があります。
街全体のポイ捨てを減少させられるかどうかは、設置場所や設置する数などによっても異なると言えるでしょう。
コストの問題
それから、大きな課題として挙げられるのが、コストの問題です。
成功例の中には、指導員によるパトロールがありました。
成功例の中では、警備会社に委託していましたが、委託するとなると当然ですが、コストの問題が出てきます。
施設や自治体などで具体的な対策を行おうと考えても、予算が限られている場合が多いため、コストの問題から十分な対策ができないという場合もあるようです。
こちらも大きな課題と言えるでしょう。
意識改革や罰則の強化の検討も必要
今回のコラムでは、タバコポイ捨て対策の成功例や課題について解説しました。
ポイ捨てを減少させるためには、その他にどのようなことが必要となるのでしょうか?
喫煙者の意識改革
喫煙者の中には、吸い殻をポイ捨てすることを悪いと思っていない人も多いと考えられます。
ポイ捨てすることによって、火災のリスクや環境汚染のリスクがあること、また他人に迷惑をかけることになるということを理解できていないのです。
そのため、喫煙者の意識改革が必要と言えるでしょう。
また、タバコの吸い殻のポイ捨ては、法律違反ですので、犯罪となります。
このことを正しく理解できている喫煙者が非常に少ないのです。
意識改革を行わなければ、ポイ捨てを減少させることは難しくなってしまいます。
罰則の強化
喫煙者の意識改革の他には、罰則の強化を検討するというのもよいでしょう。
罰則を強化することで、ポイ捨ての抑止力となる可能性があるからです。
ポイ捨てをすると、高額な罰金を払わなくてはならないなどとなれば、ポイ捨てをする人が大幅に減少する可能性があります。
ですから、現在の法律の見直しや罰則の強化の検討を行うのもよいでしょう。
まとめ
タバコの吸い殻のポイ捨ては、火災のリスクや環境汚染のリスクがあります。
そのため、十分な対策が必要です。
対策の成功例には、投票型喫煙所の設置やポスターの掲示、指導員によるパトロールなどがあります。
ですが、対策には課題もあり、ポイ捨てを減少させるには、喫煙者の意識改革や罰則の強化の検討などが必要となるでしょう。