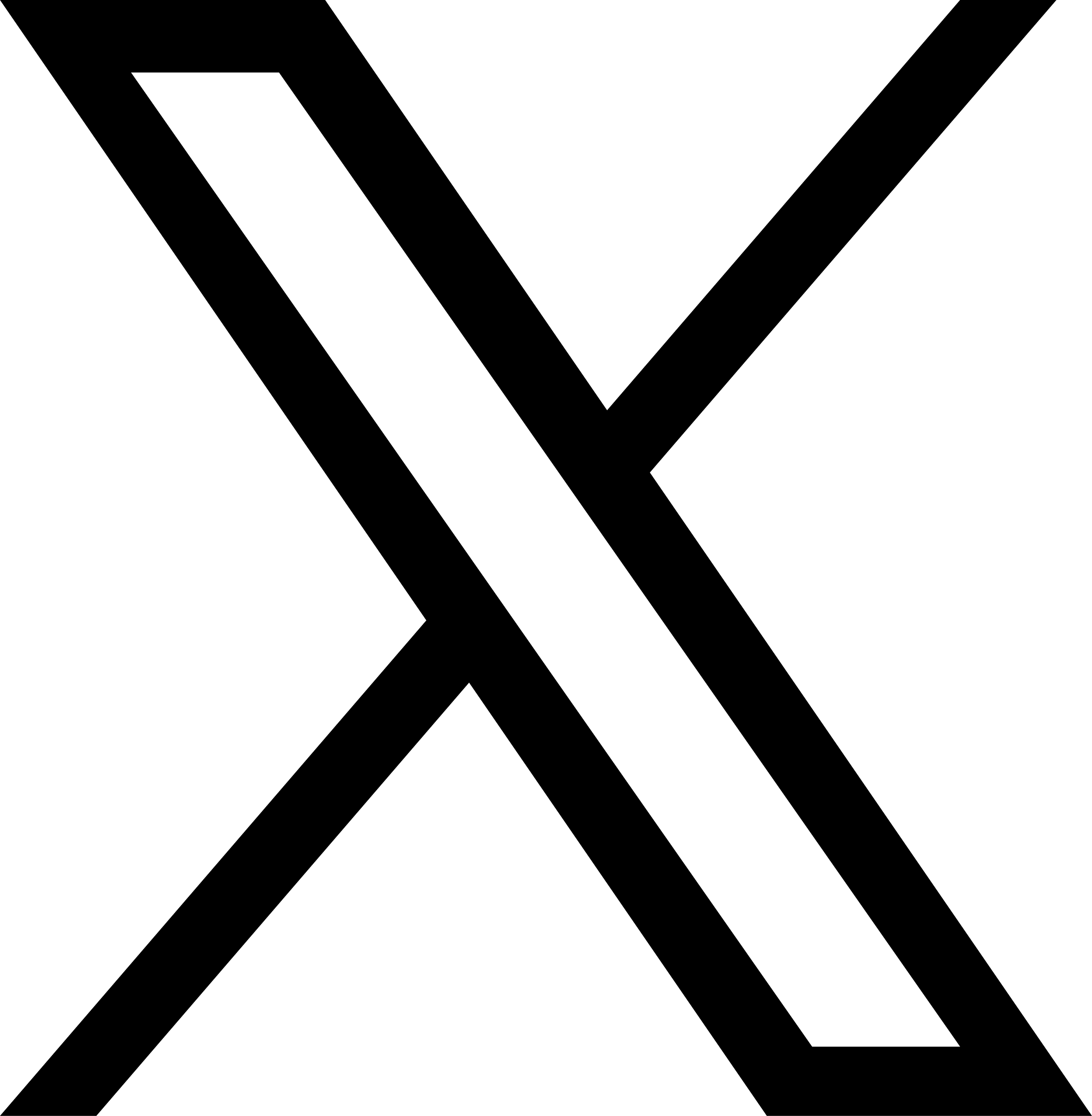ゴミステーションのカラス対策とは。被害を防ぐ3つのポイント
2021.06.30
業界コラム

都市部のゴミステーションではカラス対策が必須です。都会に順応したカラスが、生ゴミを散乱させるからです。
都会のカラスは賢く、カラス除けのネットでさえ、隙間を見つけて中のゴミが引っ張り出される場合があります。
そこで本記事では、カラス被害の実態や適切な対策方法について、東京都や環境省などの公式情報を中心に解説します。カラス対策に有効なアイテムも紹介するので、カラス対策にお困りの方はぜひ最後までご覧ください。
都市部におけるカラスのゴミ被害
都市部のカラス問題は、年々深刻化しています。増え続けるカラスによって、人への被害も増加しているのです。まずはその実例として、カラスの生息状況とゴミ被害について、東京都と兵庫県西宮市の研究報告を併せて紹介します。
カラスの生息状況
東京都環境局の資料によると、1970年代には山手線の内側でカラスの繁殖が観察されることは、ほとんどありませんでした。しかし、カラスは年々増加し続け、平成13年の研究では、都内全域で3万羽から3万5000羽と推計されるまでに。
主な要因は、エサとなる豊富な生ゴミ、天敵の少なさ、ねぐらとなるような樹林(明治神宮や自然教育園)の存在だとされています。都市部には、カラスの生息に適した条件がそろっているのです。
ゴミ被害
2013年に兵庫県西宮市で行われたアンケート調査では、「カラスから何らかの被害を受けたことのある人」は約7割でした。被害の中でもっとも大きな割合(58%)を占めるのが「ゴミの散乱」です。次いで「鳴き声がうるさい」が28.1%、「人への攻撃」が10.4%と続きました。
直接的な攻撃が10.4%を占めているのも由々しき問題ですが、やはりこの回答結果を見る限りは、ゴミの散乱がカラス被害の一番のポイントといえるでしょう。
カラスの生態からみるゴミ置き場被害
カラスによるゴミ置き場の被害は、単に「ゴミが荒らされる」というだけの問題ではなく、カラスの優れた生態や行動特性が深く関係しています。
カラスは非常に賢く、環境への適応能力や学習能力に優れた鳥であり、人間社会に巧みに入り込んでいます。ここでは、カラスの生態的な特徴を踏まえながら、なぜゴミ置き場が狙われるのか、そして被害が長期化・深刻化しやすいのかを解説します。
まず注目すべき点は、カラスの高い知能と記憶力です。
カラスは人の顔を認識できるだけでなく、一度見つけた餌場を正確に記憶し、定期的に訪れる習性があります。ゴミ収集の時間帯や人の行動パターンも把握しており、住民がゴミを出した直後を狙って飛来するケースが多く見られます。このような「学習行動」により、適切な対策を講じていないゴミ置き場は、継続的に被害を受けやすくなります。
さらに、カラスは社会性の強い鳥でもあります。単独で行動することもありますが、多くの場合は群れで情報を共有し、餌場をめぐる行動にも協力が見られます。1羽のカラスがゴミ置き場を荒らし始めると、周囲のカラスもそれを学習し、同じ場所に集まるようになるのです。こうした「伝播性」が、被害の拡大を招く要因となっています。
また、カラスは雑食性で、特に生ゴミに含まれる肉や魚のにおいに敏感です。人間が「臭い」と感じるものほど、カラスにとっては魅力的な餌です。そのため、ゴミ袋の中身が見えていたり、においが漏れていたりすると、格好のターゲットになります。視覚と嗅覚をフル活用し、袋をつついて簡単に中身を取り出してしまうのです。
このような生態を踏まえると、ネットをかけただけの対策では十分とは言えません。たとえば、ネットに少しでも隙間があると、カラスはそこを見つけて器用にゴミ袋を引き出すことができます。また、ネットが軽量すぎる場合、カラスがネットをめくって中に入ることもあります。つまり、「見た目だけの対策」はすぐに見破られ、学習されてしまうということです。
こうした理由から、カラスの生態を理解した上で実効性の高い対策が求められます。カラスの優れた視覚・嗅覚・記憶力・学習能力といった特性を逆手に取り、物理的にアクセスを遮断するボックス型のごみ保管庫や、定期的に対策方法を変更するなどの工夫が有効です。
環境省も、カラス被害の抑止には「多様な手法の併用」と「慣れを防ぐ継続的な工夫」が重要であるとしています。
カラスによる被害を根本的に防ぐには、ただ対処するだけでなく、「なぜカラスがその行動をとるのか」を理解することが第一歩です。生態に即した対策こそが、長期的な被害の軽減につながります。
ゴミステーションのカラス対策が必要な理由とは
ゴミステーションには、カラス対策が必要です。対策が講じられない場合、衛生面の悪化、襲撃の増加、生態系の悪影響、景観を損なうなど、さまざまな問題が生じる可能性が高いからです。
前項では、住民目線からのゴミ被害について簡単に紹介しました。ここからは、さらに広い視点でカラスがもたらす問題と、ゴミステーションにおけるカラス対策の必要性を解説します。
1.衛生面
ゴミが散らかるだけでも不衛生ですが、ゴミステーションやねぐら付近がカラスのフンで汚れるのも問題です。カラスのフンには、人に感染する病原菌が含まれている可能性があるため、ゴミステーションがカラスの餌場になる状況は避けなければなりません。
2.襲撃防止
ハシブトガラスという種類のカラスは、特に人を攻撃します。日本鳥類保護連盟によると、特に繁殖期(5~7月)は人を攻撃しやすい傾向にあります。
3.生態系の保全
カラスの増加は他の野鳥の減少、繁殖率低下につながります。カラスは雑食性で、他の野鳥の卵やひなを捕食するからです。
実際に近年はスズメ、ツブリの繁殖率が低下し、オナガが激減した地域もあります。さらには動物園での捕食被害も報告されており、都内の動物園ではアヒルがとられたり、プレーリードッグが食べられたりした事例もあります。
4.景観の保全
ゴミの散乱やカラスのフンは、地域の景観を損ねます。都会に慣れ、人への警戒心が薄れたカラスは、周囲の人の有無に関わらず、対策されていないゴミステーションを荒らすのです。
ゴミステーションのカラス対策をしない場合は、人の生活や生態系に危害が及びます。効果の高い対策は必須といえるでしょう。
カラス被害を減らすゴミの出し方
カラス被害を減らすためには、ゴミの出し方を工夫する必要があります。
ここでは、カラス被害の防止に効果的なゴミの出し方を、いくつかご紹介します。
1.生ゴミを減らす
カラスの餌となる生ゴミを減らすことで、カラス被害を減らすことができます。食材は使いきれるだけの必要な量だけを買い、作った料理は残さず食べきるようにしましょう。また、水分を含む食材などはしっかりと水切りをすることで、カラスを寄せつけにくくできます。
2.ゴミを見えにくくする
ゴミ袋の外から生ゴミなどが見えないよう、生ゴミを新聞紙などで包んだり、カラスを寄せつけるようなゴミをゴミ袋の中心部に位置するよう詰めたりするのも効果的です。視認性だけでなく、生ゴミなどはにおいでもカラスを引き寄せるので、しっかりと水切りをしたり、ゴミの日まで冷凍庫に入れて冷凍しておいたりするのもおすすめです。
3.カラス除けグッズを使う
鳥獣ネットやネットボックスなど、カラス対策用グッズを導入するのも効果的です。ネット地のものは、できるだけネットの目が細かく、丈夫な素材で作られているものを選びましょう。
また、ネットやボックスを常設できない場合は、折りたたみ式のものや、持ち運びに便利な軽量のものを選ぶのがおすすめです。
4.黒い袋に入れる
ゴミを出す際に使用する袋の「色」も、カラス被害を防ぐ上で有効な工夫の一つです。
特に透明や半透明の袋は、中の生ゴミが視認できてしまうため、カラスにとって餌のありかを簡単に見つけられる状態です。そこで有効なのが「黒いゴミ袋」を使用する方法です。
カラスは非常に視力が良く、袋越しでも食べ物の形や色を見分ける能力を持っています。特に肉や魚など、光沢のある生ゴミは見つけやすく、狙われやすい傾向にあります。
一方、黒色の袋は中身が見えないため、カラスの視覚情報を遮断できるというメリットがあります。袋の外から食べ物の形状や色がわからないことで、ゴミを漁る行動を抑制することができるのです。
また、黒い袋はにおいもある程度抑える効果があります。完全に密封できるわけではありませんが、半透明の袋よりはにおいの漏れが少ないとされているため、視覚と嗅覚の両面からカラスの関心を下げられる可能性が高くなります。
ただし、一部自治体では透明または半透明の指定袋の使用が義務づけられている場合があります。地域のルールに従った上で、たとえば透明袋の内側に黒い袋を重ねて使用するなどの工夫をするのも一案です。
5.塀にS字フックで吊るす
地面に直接ゴミ袋を置かず、「吊るして出す」という方法も、カラス対策として一定の効果が期待できます。
特に一軒家や小規模な集合住宅などで、自宅前にゴミを出す必要がある場合は、塀にS字フックなどを活用して吊るす」ことで、カラスに荒らされにくい環境を作ることができます。
カラスは地面に置かれたゴミを狙うことが多く、高い位置にあるものに対しては接近しにくい傾向があります。吊るされたゴミ袋は、揺れたり回転したりすることで不安定に見え、カラスにとっては「捕食しにくいもの」として警戒されやすくなるのです。特に風がある日は、袋が揺れることでカラスの接近を防ぐ効果が高まります。
この方法を実践する際は、しっかりとしたフックや金具を取り付けることが重要です。耐荷重のあるS字フックやロープ、専用の吊り下げフレームなどを使い、ゴミ袋が外れて落ちたりしないようにしましょう。また、袋が破れにくいように二重にするか、厚手の袋を使うのもおすすめです。
なお、人目のある場所や監視カメラのある範囲にゴミ袋を吊るすことで、カラスだけでなく、猫や野良動物、人為的なイタズラへの抑止力にもなります。簡易的な方法ながら、物理的にカラスの行動を制限できる実践的な対策です。
カラス対策グッズの使い方
カラス被害を防ぐには、対策グッズを「正しく使う」ことが不可欠です。
ここでは、よく使用される5つのカラス対策グッズについて、基本的な使い方と注意点をご紹介します。
1.防鳥ネット
防鳥ネットはゴミの上にしっかりと覆いかぶせ、隙間ができないように四隅を重石やピンで固定しましょう。ネットの目が粗いとカラスに突かれるので、目の細かいタイプ(5mm以下)を選ぶことが重要です。
2.ボックス型ゴミストッカー
ゴミ袋を内部に完全に収納し、フタを確実に閉めて使用します。金属製のものは重さがある分、安定性に優れ、カラスによる開封を防ぎます。軽量タイプは設置が簡単ですが、風や揺れに注意してロープなどで補強しましょう。
3.吊り下げ式フレーム(S字フック)
塀やフェンスにS字フックを取り付け、ゴミ袋の取っ手部分を掛けて吊るします。カラスは高い位置の不安定な餌に近づきにくいため、地面から離すことで被害を防げます。袋が落ちないよう、しっかりと固定するのがコツです。
4.防除音声スピーカー
カラスの警戒音や天敵の鳴き声を再生する機器です。ゴミステーションの近くに設置し、タイマーまたはセンサーで自動再生させることで、カラスの接近を防ぎます。音声の「慣れ」を防ぐため、定期的な音の変更がおすすめです。
5.カラス撃退ロボット
リアルな羽ばたきや鳴き声でカラスを威嚇する装置です。ゴミ置き場の近くに設置し、できるだけカラスの視界に入る位置で使用します。定期的に設置場所や角度を変えることで、カラスの警戒心を維持することができます。
カラス対策に成功したごみ出し事例
カラス対策に有効な方法として、すでに実績がある事例がいくつかあります。確実に対策したい方は、これらのカラス対策グッズの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
防鳥ネット
防鳥ネットは、カラスによるゴミの散乱の予防に効果的なグッズとして、多くの地域で利用されています。
しかし、いくらカラス対策に有効な防鳥ネットとはいえ、ネットの目の間隔が広かったり、ゴミステーションの大きさに合っておらずゴミがはみ出してしまっていたりすると、十分な効果は期待できません。
防鳥ネットを選ぶ際は、目の間隔が5mm以下の細かいものを選ぶこと。そして、ゴミステーションやゴミ置き場、ゴミの量などに適したサイズのものを選ぶようにしましょう。
ボックス型ネット
戸建て住宅など、自宅の敷地内に自分でゴミ置き場を設置して管理する必要がある場合は、ボックス型ネットも効果的です。
常設するタイプのボックス型ネットには、金属製のタイプと軽量タイプがあります。金属製のボックスは全体が金属で構成されているため、カラスにフタを開けられたり、隙間からゴミ袋をつつかれたりする危険が少ないので安心です。しかし、重量があるため設置までが大変というデメリットも。また、軽量タイプに比べてフタが重いため、毎日のゴミ出しとなると、お年寄りや小柄な女性には少し大変かもしれません。
一方、軽量タイプのボックス型ネットは、ネット部分がポリエチレン製でフレームがアルミ製のタイプが多く、設置がしやすく扱いやすいという利点があります。ただし、金属製のタイプほどの堅牢性はありません。
それぞれ、用途や設置場所、環境条件などと照らし合わせ、適したものを導入しましょう。
カラス対策には「ボックス」が有効
都会のカラスには、カラス除けネットが通用しない場合があります。知恵がついた個体は、ネットの隙間からゴミを引っ張り出してしまうのです。
そこでおすすめなのが「ボックス」です。
ボックスには複数の種類があるので、それぞれの特徴をご紹介します。
ワイドペールシリーズ

ワイドペールシリーズは、耐久性・耐候性・容量に優れたボックスです。大きなサイズでは1500ℓ(45ℓポリ袋が約33個分)の容量があります。カギ穴付きなので、カラスはもちろん、防犯対策にも最適な製品です。大きなサイズではありますが、キャスター付きのものもあり、移動しやすい設計になっています。
また、強風時の固定や盗難対策として、ロープで止めるための「アイボルト」が付属しています。さらに、排水口が付いているなど、大きなサイズでも掃除がしやすい構造になっているのがメリットです。
ワイドステーションシリーズ

ワイドステーションTWは、丈夫なステンレス製のボックスです。ゴミの投入口がスライド式で、開閉がゆっくりになるダンパーが付いており、ゴミを安全かつスムーズに投入できるのが特徴です。
一方、ワイドステーションRは、折りたためるタイプのボックスです。丈夫でサビにも強いというメリットのほか、コンパクトに収納できるのもポイント。投入口が観音開きになるのも特徴です。
関連商品:ワイドステーション TW-550
ワイドストレージシリーズ

ワイドストレージシリーズは、二重壁パネル構造の衝撃に強いボックスです。樹脂製容器なのでサビません。サイズは、400ℓと600ℓのものがあります。また、ワイドシリーズと同じく排水口とカギ穴が設けられているため、掃除がしやすいほか、防犯やカラス対策にも役立ちます。
関連商品:ワイドストレージ 600キャスター付
ラク折りくん

ラク折りくんは折り畳み式の保管枠で、手軽に設置や収納ができるのが特徴です。重量は65㎏で、容量は1300ℓ。亜鉛メッキがされているのでサビにくい仕様です。アスファルト面に設置するときはアンカーで固定します。
関連商品:ラク折りくん 800
自立ゴミネットシリーズ

自立ゴミネットシリーズは、軽くて持ち運びが簡単な自立ネットタイプのボックスです。重さ約2㎏で、折りたたみ可能なコンパクト設計ですが、カラスからの攻撃を効果的に防止できます。
材質はネット部分がターポリン、支柱がFRP、取っ手・枠がポリエチレンです。さらに外から中身が見えるので、分別収集にも役立ちます。容量については250ℓから730ℓまで、さまざまなサイズを販売しています。
その他のカラス対策

ここまでご紹介したカラス対策グッズの他にも、ユニークなカラス対策グッズがあります。「カラス対策グッズをいろいろと試してみたけど、期待以上の効果がない……」「念のために打てる手をすべて打っておきたい」という方は、本項でご紹介するカラス対策グッズの導入も検討してみるとよいでしょう。
カラス専用防除機
スピーカーからカラスの声を出し、本物のカラスを追い払う防除機です。スピーカーをゴミステーションに設置して使います。
細かい仕様はメーカーによって異なりますが、特殊な状況下にあるカラスの鳴き声を、スピーカーから発してカラスを牽制する仕組みです。具体的には「カラスが天敵に襲われて苦しんでいる声」などです。天敵に捕食されているカラスの悲鳴が、本物のカラスを警戒させ、追い払います。
他にも赤外線センサーでカラスを感知し、適切なタイミングでカラスの警戒心をあおる音声を流す製品もあります。センサーの反応範囲は3~4メートルに達するので、ゴミステーションで高い効果を発揮します。さらにカラスの「慣れ」に対応するために、音声交換サービスを提供しているメーカーもあります。
カラス撃退ロボット
栃木県宇都宮市の企業が研究開発している、対カラス用のロボットです。光を通さない特殊なシートにカラス型ロボットが包まれているような外観で、カラスの羽だけがバタバタと動き、周囲のカラスを牽制します。カラスからすれば、瀕死のカラスが袋に詰められているような姿に見えるかもしれません。さらに、生命の危機にあるような声をロボットが発することで、周りのカラスに警戒心を与えます。
特徴的なのは、羽の部分に本物のカラスの羽を使っていることです。ロボット部分はシートで隠し、羽だけで本物だと錯覚させる仕組みです。カラスの目は紫外線を認識できるので、普通のゴミ袋の中身は探り当てられます。そうしたカラスの性質に対策するため、特殊なシートを採用しているわけです。
カラスのゴミ被害には臨機応変な対策を
今回は、カラスによるゴミ被害と、代表的な対策方法についてまとめました。
東京都ではカラス対策が推進されているとはいえ、いまだに衛生管理や襲撃防止、生態系の保全、景観の保護などは、人間社会にとって厄介な問題であることに変わりありません。
また、環境省の資料によると、カラスは学習能力が高く、単一的な対策では「慣れ」が生まれてしまいます。
今回ご紹介したボックスなどの強力な対策方法を活用したり、さまざまな対策を使い分けたりして、カラスを慣れさせないことが重要です。
関連コラム
-

-
業務用掃除機は家庭用と何が違うの?
正しい選び方とおすすめ掃除機を紹介掃除機における業務用と家庭用の違いは、主に吸引力と耐久性、容量の3つにあります。本記事では、オフィスや工場、ホテルなど、現場に合った業務用掃除機の選び方を徹底解説。種類や用途、注意点も分かり、貴社にぴったりのおすすめの掃除機が見つかります。
-

-
失敗しない業務用ゴミ箱の選び方
|知っておくべきポイントとおすすめ商品店舗やオフィスに最適な業務用ゴミ箱の選び方を解説。容量・素材・機能といった基本のポイントから、設置場所ごとの選び方まで分かりやすく紹介。テラモトの「ニートシリーズ」など、おすすめ商品も多数掲載しています。
-

-
業務用テントの正しい選び方!
現場担当者が知っておくべき5つのポイントとおすすめ商品業務用テントの失敗しない選び方を5つのポイントで解説。形状・サイズ・素材選択からメンテナンス方法まで、専門知識不要で適切な商品選びができる実践ガイドです。安全で効率的な業務環境実現のための、実践的な選択方法をご紹介します。
-

-
二酸化炭素中毒を防ぐために│CO2濃度の基準値と対策を徹底解説