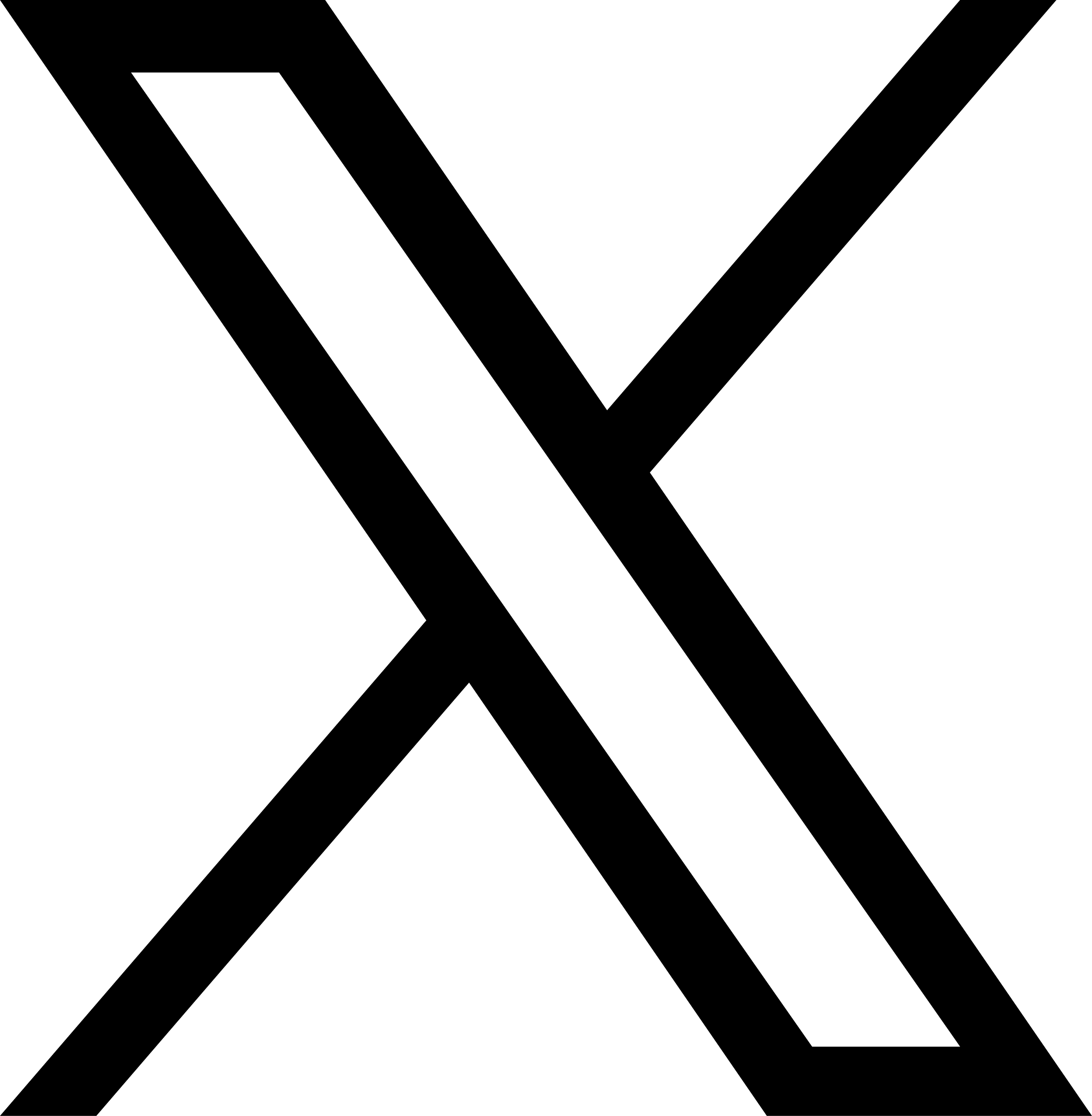「HACCP(ハサップ)」 という言葉を、知っていますか?――今知っておきたい、衛生管理の基本
2022.02.09
業界コラム

一般的には聞きなれない言葉――「HACCP(ハサップ)」は、食の安全を確保するために取り決められた衛生管理の制度です。
その「HACCP(ハサップ)」が、2021年6月に義務化されました。
食品の製造、加工、調理、販売を行うすべての事業者が対象となっています。
もちろん衛生管理は義務化される前から多くの食品工場などで、積極的に取り組まれてきました。
今回の制度の義務化では、小規模な工場や製造・加工者、飲食店等にも「HACCP(ハサップ)」に沿った衛生管理に取り組むことが必要です。
そして「HACCP(ハサップ)」の衛生管理を知ることは、一般家庭での料理や保存の安全を守る意識を高めるヒントがたくさんあります。
「HACCP(ハサップ)」とは?
「HACCP(ハサップ)」とは、一言で表すなら、食品製造を管理し、安全性を確保するためのシステムです。衛生管理に必要なことを表す英単語5文字から名づけられ、HACCP(ハサップ)システムとも呼ばれています。
H:Hazard ハ ザ ー ド(危険となる要因)
A:Analysis アナリシス(分析すること)
C:Critical クリティカル(重要なこと)
C:Control コントロール(管理する)
P:Point ポイント(場所、過程)
HACCP(ハサップ)システムは、「危害要因分析」と「重要管理点」の2つの柱で取り組みます。
危険となる原因を調査・分析する(HA)
食品加工・販売等を行ううえで、原材料から調理方法・保管方法・出荷までの各工程ごとに、食中毒や異物混入、有害化学物質など人体への健康被害となるおそれのある原因がないか、調査すること。
危険となる可能性を予測・監視する(CCP)
健康被害となりえる原因の除去や低減のために、直接管理できるポイントを継続的に記録管理し、事故を未然に防ぐこと。
身近な例で考えてみる、HACCP(ハサップ)システム
HACCP(ハサップ)システム――簡単にまとめてみましたが、食品加工などに携わっていない多くの人にとってはなかなかイメージが難しいもの。
そこで、身近な料理の調理を通して「HACCP(ハサップ)システム」をイメージしてみましょう。
【ハンバーグを作りに「HACCP(ハサップ)」を当てはめる】
「危害要因分析」
・ハンバーグの材料(ひき肉、玉ねぎ、卵など)に、食中毒の要因となる菌が潜んでいる時がある。
・適切な保管方法・調理方法を行わなかった場合、食中毒や異物混入の要因が発生する。
・調理時に髪をまとめていなかったなど、危険要素・異物混入の可能性がある。
「重要管理点」
・材料の新鮮さや保管方法をきちんと把握する。
・調理をする過程(ハンバーグの肉が生焼けにならない適切な加熱温度で焼く、野菜はよく洗う等)で、危険要素をなくす。
・調理の際の衛生管理(手指・調理器具の洗浄、髪をまとめる等)を、調理過程に合わせて実施する。
・料理を提供する、保存する際の衛生管理(皿・容器などは清潔か、適した温度で保管されているか、賞味期限は守られているか等)を実施する。
このように「なにが危険要素(食中毒・異物混入など)となるか」を知り、「どのタイミングで何をすれば危険要素をなくす・少なくできるか」を実施することがHACCP(ハサップ)システムの基本的な考えです。
継続的に管理・監視・記録を行うことで、もし問題が起こった場合はいつ・どこで・何が要因だったかをすぐに把握できます。
意外なスタート、「HACCP(ハサップ)」が生まれたわけ
「HACCP(ハサップ)」が誕生したのは、1960年ころのアメリカ合衆国――なんとそのきっかけは、宇宙開発アポロ計画でした。
宇宙ではすべての面において安全性が重要です。
もちろん、宇宙飛行士が食べるものは100%の安全を目指さなければなりません。
それまでの食品加工の衛生管理は、出来上がったものを抜き打ちで検査し、
危険性がないかを調べていました。しかしその方法では、出来上がった食品すべての安全性を保障できませんでした。
そこで、NASA・アメリカ合衆国陸軍・大手食品メーカーが協力し、宇宙飛行士の食品を加工するために考えたシステムが「HACCP(ハサップ)」です。
この衛生管理システムは、その後多くの企業に導入されました。
HACCPと従来の検査の違い
HACCP以前の衛生管理では、完成した製品の一部を抜き取って検査する「抜き取り検査」が主流でした。しかし、この方法では検査対象外の製品に不良品が混ざる可能性を完全に排除できませんでした。
一方、HACCPは「製造工程そのもの」を管理します。危険要因をあらかじめ予測し、発生しそうなポイントを事前に制御することで、不良品を未然に防ぐのが特徴です。
つまり、製品完成後の検査ではなく、「作る過程で安全性を確保する」ことが、HACCPの大きな特徴なのです。
日本における「HACCP(ハサップ)」の変遷
日本で本格的に「HACCP(ハサップ)」をもとにした衛生管理が取り入れられたのは、1996年。
厚生省が食品衛生法を改正し、『総合衛生管理製造過程』制度を導入しました。
同年、大阪府堺市で発生した大規模な食中毒O-157は、記憶にある人も多いと思います。
その後、「HACCP(ハサップ)」は食品製造業や輸出業者が導入する制度として広まっていきましたが、2015年3月から、飲食店への導入義務化を目指した条約改正が段階的に始められました。
そして2021年6月、食品製造業者だけでなく、飲食店・小売店・製造者・物流などが、事業規模の大小にかかわらず「HACCP(ハサップ)」の導入義務の対象となりました。
管理基準が厳しくなったぶん、小規模な製造者への負担は少なくありません。
秋田の「いぶりがっこ」や沖縄の「島豆腐」など、地方文化を担う郷土料理を作って販売している小規模な販売者は、存続の危機に直面しています。
HACCPの義務化について
2021年6月のHACCP義務化は、食品業界全体にとって大きな転換点となり、消費者がより安心して食品を選べる環境整備が進められています。
義務化の背景には、食の安全性に対する国際的な基準の統一や、海外輸出時の信頼確保といった課題がありました。日本国内でも、食品事故のリスクを未然に防ぎ、事業者ごとの衛生管理レベルの差をなくすことが狙いです。
この義務化に伴い、すべての事業者は規模に応じた「HACCPに基づく衛生管理」または「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を実施する必要があります。大規模な工場と個人経営の飲食店では対応方法に違いがありますが、いずれも「危険要因を予測し、記録・管理して防ぐ」という考え方は共通です。
「HACCP(ハサップ)」はただ衛生管理するだけでなく、意識を変えること。
「HACCP(ハサップ)」は、食の安全を守るための厳しい衛生管理システムです。
しかし、衛生管理は工場や店舗の責任者だけが行いマニュアル化するだけでなく、そこで働く人すべてに共有できていないと徹底することが難しいものです。
そこで再度知っておきたいのが「5S」というスローガン。
主に製造業、サービス業などの職場環境改善のために呼びかけられることも多いですが、学校などで習うこともあります。
「5S」を知り意識することは職場だけでなく、家庭の環境改善にも繋がるので、ぜひチェックしてみましょう。
整理
必要なもの・いらないものを見極め、不要なものは捨てる。
物理的なものだけでなく、情報や行動、時間などさまざまなものが対象となる。
整頓
物の「住所」を決め、定められた位置に置くこと。全員が把握し、必要なときにすぐに取り出せるようにすることで、作業上の無駄な時間を少なくできる。
清掃
身の回りをこまめに掃除すること。ゴミを減らすだけでなく、スペースの有効化や整頓のしやすさ、万が一の災害時に対する危険を低減する。
清潔
整理・整頓・清掃を継続的に行い、きれいな状態を保つこと。清潔さをキープすることは衛生管理や品質・能率向上だけでなく、昨今の感染症対策にも欠かせない。
習慣化
決められたルールや手順を正しく守り、継続的に行うこと。
「HACCP(ハサップ)」とは何かを知り、それを守るために必要なこと。
そこには食品加工や製造・販売に関わる人たちだけでなく、すべての職場や家庭でも活かせるヒントがたくさんつまっています。
HACCPを構築するための7原則12手順
HACCPシステムは、計画的かつ継続的な衛生管理を行うために「7原則12手順」として体系化されています。
まず、製造する食品や工程を正しく理解する準備段階(12手順のうち前半)を経て、7つの原則に沿って具体的な管理を実施します。
それぞれの原則には、現場での管理・記録・改善が欠かせません。
原則1:危害要因の分析
原材料や製造・加工工程で、食中毒菌や異物混入、有害化学物質などの危険要因(ハザード)を洗い出し、どの工程で発生する可能性があるかを分析します。これにより、食品事故のリスクを事前に把握します。
原則2:重要管理点(CCP)の決定
危害要因を確実に抑えるために、特に重点的に管理する工程や場所(重要管理点=critical control point、CCP)を決めます。たとえば「加熱」「冷却」「金属探知機による検査」などが該当します。
原則3:管理基準(CL)の設定
CCPごとに「これ以下なら安全」と判断できる基準(管理基準=critical limits)を数値や状態で明確に設定します。たとえば、加熱時の中心温度や冷却時間などがこれにあたります。
原則4:モニタリング方法の設定
各CCPが管理基準を満たしているかどうかを確認する方法(モニタリング)を決め、実際に記録します。温度計測や目視確認など、現場で確実に実施できる方法を選びます。
原則5:是正措置の設定
モニタリングの結果、管理基準から外れた場合にどう対応するか、事前にルールを決めておきます。不良品の廃棄や再加熱、作業手順の見直しなどが含まれます。
原則6:検証手順の確立
HACCPプランがきちんと機能しているかどうか、定期的に検証します。検査や社内監査、第三者機関によるチェックなどが有効です。検証によって必要であれば改善も行います。
原則7:記録と文書管理の実施
各管理工程や検証、是正措置などの結果を記録し、文書として保存します。これにより、万が一事故が起きた場合でも、原因究明や再発防止に役立ちます。
HACCP(ハサップ)は、食品の安全性を確保するために極めて効果的な管理手法として世界中で導入されています。ただ単に食品事故を防ぐだけでなく、企業の信頼性向上や国際的な競争力の強化、さらには従業員の衛生意識の底上げなど、幅広い効果をもたらします。ここでは、HACCPがもたらす主なメリットとその実際の効果について具体的に見ていきましょう。
HACCPのメリットとその効果
HACCP(ハサップ)は、食品の安全性を確保するために極めて効果的な管理手法として世界中で導入されています。ただ単に食品事故を防ぐだけでなく、企業の信頼性向上や国際的な競争力の強化、さらには従業員の衛生意識の底上げなど、幅広い効果をもたらします。
ここでは、HACCPがもたらす主なメリットとその実際の効果について具体的に見ていきましょう。
食品事故の予防と安全性向上
HACCPの最も大きな効果は、食品事故を未然に防ぐことにあります。
従来の「完成品を検査して不良品を見つける」という方法では、事故が発生するまで問題が見逃されることがありました。しかし、HACCPでは製造や加工の過程で危険要因を事前に分析し、発生しやすい工程を重点的に管理します。
これにより、異物混入や食中毒菌の繁殖といったリスクを根本から抑えることができ、安全な製品の提供が可能になります。
また、継続的なモニタリングや記録管理によって、工程ごとの問題を早期に発見し、改善するサイクルが確立され、食品の安全性がさらに高まります。
消費者からの信頼獲得
食品に対する消費者の目は年々厳しくなっており、衛生管理の取り組みは企業の信頼性に直結しています。
HACCPを導入することで、事業者は「食の安全」に対して科学的・体系的に取り組んでいることを示すことができます。
特に食品表示や公式ウェブサイトなどでHACCP認証取得や衛生管理方針を明示することにより、消費者に安心感を与えることができます。
また、万が一問題が発生した場合でも、原因を迅速に突き止め再発防止策を講じる体制が整っているため、危機管理能力の高さも評価されやすくなります。
こうした取り組みは、リピーターの獲得やブランド価値の向上につながる重要な要素となっています。
国際取引や輸出での優位性
HACCPは、食品安全の国際標準として多くの国や地域で採用されています。特にアメリカやEU、アジア各国などでは、HACCPによる衛生管理を輸入条件として義務づける場合もあります。そのため、日本国内でHACCPを導入していないと、海外市場への輸出が難しくなることもあります。
一方、HACCPを導入・運用している企業は、国際基準を満たしていることが証明され、海外の取引先からの信頼を得やすくなります。さらに、貿易交渉や国際展示会でのアピール材料にもなり、海外展開を進める上で競争優位性を確保できる重要な要素です。
グローバルな食品ビジネスを目指す企業にとって、HACCPの導入は必須と言えるでしょう。
従業員の衛生意識向上
HACCPの導入は、単にマニュアルや仕組みを整えるだけではなく、現場で働く従業員一人ひとりの衛生意識を高めることにもつながります。
危険要因の把握や重要管理点での作業が日常業務となることで、「なぜその作業が必要か」を理解し、主体的に衛生管理に取り組む姿勢が育まれます。
また、モニタリングや記録作業を通じて、自分の行動が食品安全に直結していることを実感しやすくなります。
このような意識の向上は、衛生管理だけでなく職場全体の品質管理能力や安全文化の向上にもつながり、組織全体の信頼性や生産性の向上にも良い影響をもたらします。
製造・販売の効率化とコスト削減
HACCPの仕組みを導入することで、食品製造や販売に関わる業務のムダを見直し、効率的な運用が可能になります。
危害要因を把握したうえで、重点的に管理するポイント(CCP)に絞って衛生対策を行うため、必要以上に全工程で過剰な管理をする必要がなくなります。その結果、人手や時間、衛生資材などのコストを抑えつつ、安全性の高い製品づくりが実現できます。
また、トラブルが発生した場合も、原因を早期に突き止めて再発防止ができるため、大規模な製品廃棄や回収といった事態を未然に防ぎ、長期的にはコスト削減につながります。
このようにHACCPは、品質向上とコスト管理の両立を可能にする仕組みなのです。
HACCPの課題と導入時の弱点
HACCPは非常に優れた食品衛生管理システムですが、すべての事業者にとって完璧な仕組みではありません。特に中小企業や個人事業者にとっては、導入や運用に関して多くの課題が存在します。制度としての有効性と現場の実情との間にギャップが生じることも少なくありません。
ここでは、HACCP導入にあたっての主な弱点や課題を整理し、注意すべきポイントについて考えていきます。
小規模事業者への負担
HACCPの義務化により、規模の大小を問わずすべての食品関連事業者が衛生管理に取り組む必要があります。しかし、小規模な食品製造者や個人経営の飲食店にとって、HACCPの考え方を取り入れることは大きな負担となる場合があります。
特に人員や予算が限られている事業者では、危害要因分析やモニタリング、記録管理などの作業を日常業務に組み込む余裕がないこともあります。
また、地方の伝統食品や小規模生産者では、従来の方法を変更することが文化や技術の継承に影響を及ぼすという懸念もあります。
行政や業界団体による支援策はありますが、実際の現場では人手不足やコスト負担の増大に直面し、HACCP対応が事業存続の課題となっているケースも少なくありません。
初期導入コストと教育の難しさ
HACCPの導入には、システム構築や設備投資、マニュアル整備など初期段階で多くのコストが発生します。大規模事業者であれば専門部署やコンサルタントの活用が可能ですが、中小企業や個人経営では大きな経済的負担となることがあります。
さらに、従業員への教育も重要な課題です。
HACCPの正しい運用には、すべてのスタッフが衛生管理の必要性や具体的な作業内容を理解していることが不可欠ですが、食品衛生の知識が十分でない現場では、教育や意識改革に時間がかかります。
特にアルバイトや短期雇用が多い業種では、教育を継続的に行わなければならず、人材の流動性の高さが導入のハードルとなります。
こうした教育・訓練の体制づくりは、HACCP導入後も継続的な課題となるでしょう。
管理や記録作業の煩雑さ
HACCPでは、製造・加工の各工程で管理状況を日々モニタリングし、その結果を記録として残すことが求められます。これにより、万が一問題が発生した場合でも、原因追及や改善が迅速に行えるという利点がありますが、現場の負担は決して小さくありません。
温度や時間の記録、清掃・点検の履歴、是正措置の実施状況など、多くの管理項目を日常的に記録し続ける必要があるからです。
特に人手不足の現場や繁忙期には、こうした作業が後回しにされたり、記録漏れが発生したりするリスクもあります。
最近ではデジタルツールによる効率化も進んでいますが、コストや操作習熟度の問題から、すべての現場で導入できるわけではありません。正確な管理と業務負担のバランスをどう取るかが課題となっています。
人手不足や属人化リスク
食品業界では慢性的な人手不足が課題となっており、HACCPの運用にも大きな影響を与えています。
危害要因の分析や重要管理点のモニタリング、記録作業などは、一定の専門知識と経験が必要ですが、現場ではそれらを担える人材が限られているケースが少なくありません。そのため、特定の従業員に業務が集中し、その人が休職・退職した場合に管理体制が崩れてしまう「属人化」のリスクも高まります。
また、パートタイム従業員やアルバイトに十分な教育が行き届かず、管理レベルにバラつきが生じることもあります。
こうした状況を防ぐためには、マニュアルや教育体制を整備し、誰でも一定レベルの管理ができる仕組みを作ることが不可欠ですが、それにも時間と労力が必要であり、導入直後は課題となることが多いです。
システムの過信による盲点
HACCPは高い効果を持つ管理手法ですが、「HACCPを導入しているから安全だ」と過信してしまうことも、実は大きなリスクです。
HACCPは、適切に運用・改善し続けることで初めて効果を発揮する仕組みであり、導入しただけで完全な安全が保証されるものではありません。
たとえば、管理基準の設定ミスやモニタリング不備、現場でのルール逸脱など、人のミスや運用の形骸化によって事故は発生します。
また、過去に発生していない新たな危害要因が見落とされる場合もあります。
そのため、HACCPの運用に満足せず、常に現場状況や社会環境の変化に応じて見直し、改善する姿勢が重要です。
システムに頼りすぎず、人の目と意識を働かせることが、食品安全を守る最後の砦なのです。
関連コラム
-

-
業務用掃除機は家庭用と何が違うの?
正しい選び方とおすすめ掃除機を紹介掃除機における業務用と家庭用の違いは、主に吸引力と耐久性、容量の3つにあります。本記事では、オフィスや工場、ホテルなど、現場に合った業務用掃除機の選び方を徹底解説。種類や用途、注意点も分かり、貴社にぴったりのおすすめの掃除機が見つかります。
-

-
失敗しない業務用ゴミ箱の選び方
|知っておくべきポイントとおすすめ商品店舗やオフィスに最適な業務用ゴミ箱の選び方を解説。容量・素材・機能といった基本のポイントから、設置場所ごとの選び方まで分かりやすく紹介。テラモトの「ニートシリーズ」など、おすすめ商品も多数掲載しています。
-

-
業務用テントの正しい選び方!
現場担当者が知っておくべき5つのポイントとおすすめ商品業務用テントの失敗しない選び方を5つのポイントで解説。形状・サイズ・素材選択からメンテナンス方法まで、専門知識不要で適切な商品選びができる実践ガイドです。安全で効率的な業務環境実現のための、実践的な選択方法をご紹介します。
-

-
二酸化炭素中毒を防ぐために│CO2濃度の基準値と対策を徹底解説