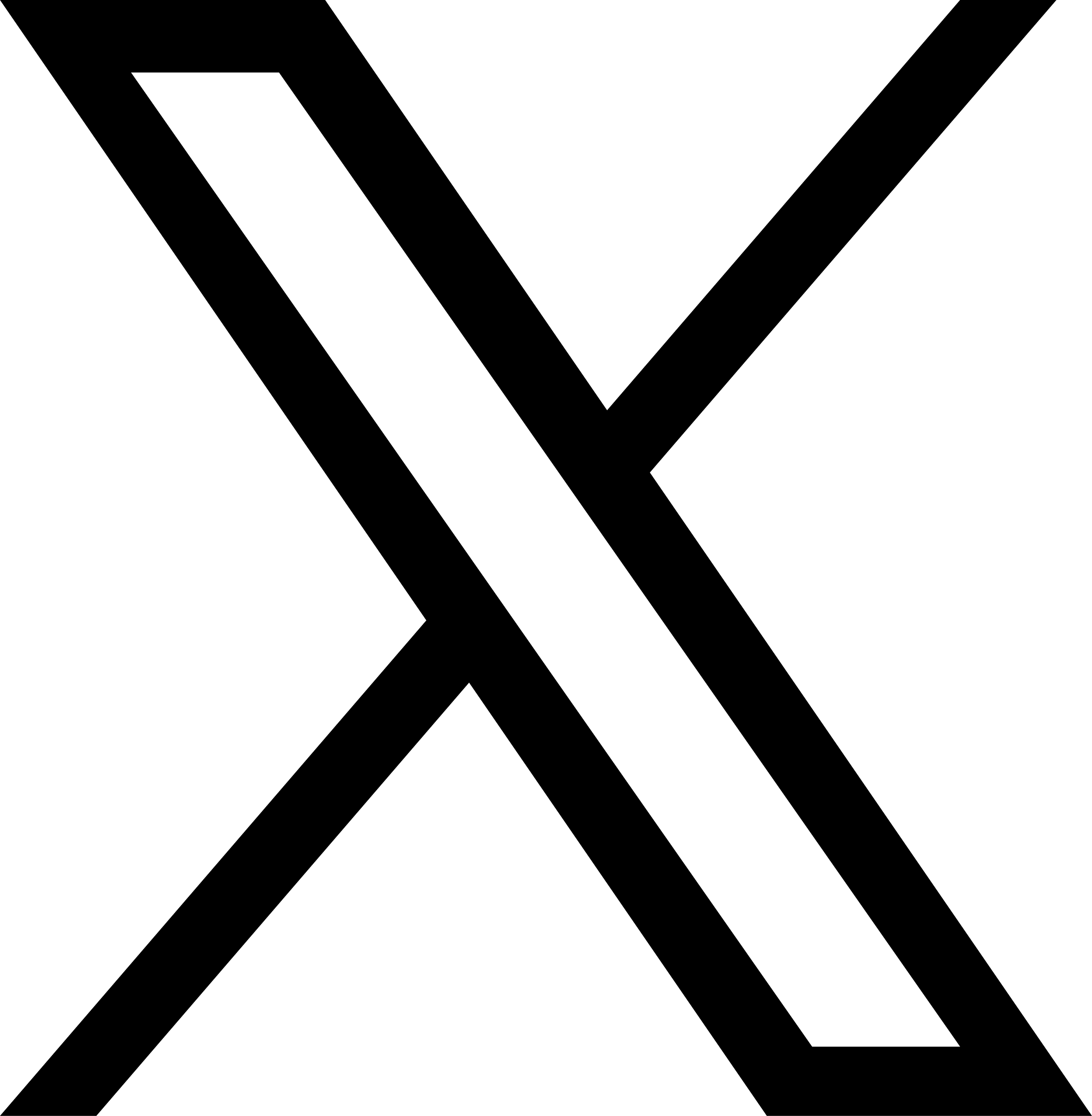フローリング・カーペット・絨毯など。花粉症予防につながる床掃除の4つのポイント
2021.02.03
お掃除コラム
商品紹介コラム

コロナ禍において、花粉症の症状は周囲に余計な警戒心を抱かせる可能性があります。また、自身が心地よく生活するためにも花粉症予防は大切です。しかし、薬を飲んでも効果がない人もいるのではないでしょうか。そこで今回は花粉症予防に繋がる床掃除について、ハウスクリーニング会社等の情報をもとに解説します。簡単に実践できる掃除のコツに加え、おすすめの商品を紹介するので、ぜひご確認下さい。
【こちらの記事も読まれています】
・今年もやってきた!黄砂の影響と屋内で掃除、清掃すべき場所とは!
・花粉症の予防はまず掃除から!掃除すべき場所と掃除機の使い方とは!
花粉はなぜリビングに集まりやすいのか?
花粉症対策として掃除が重要と言われますが、そもそも花粉にはどのような特徴があり、なぜリビングなど特定の場所に多く集まりやすいのでしょうか。まず花粉の基本的な性質から見ていきましょう。
スギやヒノキなどの植物が放出する花粉は、直径30マイクロメートル前後の微細な粒子で、非常に軽く空中を浮遊しやすい性質を持っています。風に乗って何十キロも飛ぶことがあり、春先には大量に飛散します。一度衣服や髪に付着すると、そのまま家の中に持ち込まれ、空気中に舞い上がるのです。
特に花粉はリビングに集まりやすいですが、それにはいくつかの理由があります。
まず、リビングは家族全員が長時間過ごす場所であり、出入りが多く、ドアの開閉も頻繁です。そのため、屋外から持ち込まれた花粉が落ちやすく、さらに人の動きで空気が撹拌され、床や家具に付着します。布製のソファやラグマットなど繊維の多い家具類も、花粉が留まりやすいポイントです。特に窓の開閉や換気をした際に風の流れが発生すると、空気中の花粉が一気にリビングに滞留するケースもあります。
また、日本国内における花粉飛散量の変化にも注目が必要です。近年の研究によると、花粉の飛散量は1990年代以降、気温の上昇やスギ林の成熟により増加傾向にあります。特に東京や神奈川などの都市部では、都市のヒートアイランド現象も影響し、花粉の飛散量・飛散期間ともに伸びる傾向が見られます。さらに、温暖化の影響でスギの花粉飛散開始時期が早まり、シーズンが長期化する地域も増えています。
このように、花粉は単に「外で飛んでいるもの」ではなく、私たちの生活空間に入り込み、リビングのような空間に滞留しやすいという特性があります。そのため、空気清浄機に頼るだけでなく、床掃除や布製品のこまめなケアが大切です。
今後も花粉の飛散が増える可能性を考えると、日常的な対策がより重要になるでしょう。掃除の頻度や道具の使い方を見直し、家の中に花粉を「入れない」「溜めない」習慣を身につけることが、花粉症の症状を軽減する鍵です。
花粉を家に入れないための予防策
室内の花粉対策には掃除も重要ですが、そもそも「家の中に花粉を持ち込まないこと」がもっとも効果的な予防策です。外出時の服装や帰宅後の行動を少し工夫するだけで、室内の花粉量を大幅に減らすことができます。
たとえば、外出時は花粉が付きにくい素材の衣服を選ぶようにしましょう。ウールやフリースのような起毛素材は花粉が付着しやすいので避けるようにし、ポリエステルなど表面がツルツルとした化繊のアウターを着用すると効果的です。また、髪の毛にも花粉は付着しやすいため、帽子をかぶったり、髪をまとめたりするのも有効です。
帰宅時には玄関先で花粉を払い落とすよう意識しましょう。洋服用ブラシや粘着クリーナーを使って衣類の花粉をしっかり除去した上で、室内に入るのがおすすめです。できれば上着は玄関に近い場所にかけ、室内に持ち込まないようにするとさらに効果的です。
換気のタイミングにも注意が必要です。花粉の飛散が多い日中は避け、朝早くや夜間の風が穏やかな時間帯に短時間だけ換気を行うようにすると、室内への花粉の侵入を最小限に抑えることができます。空気清浄機との併用もおすすめです。
掃除をするのは朝がおすすめ!
花粉対策の掃除は、朝の時間帯に行うのがもっとも効果的です。花粉やハウスダストは夜の間に床へ落ちてくるため、朝一番なら空中に舞い上がる前に除去しやすくなります。また、掃除は「上から下へ、奥から手前へ」の順が基本です。最初に棚や家具の上を拭き、その後で床の拭き掃除や掃除機がけを行いましょう。掃除機の使用は、床のホコリが舞わないように静かに、吸引力を弱にして行うのがポイントです。こうした順序と時間帯を意識するだけで、効率よく花粉を除去できます。
床掃除のポイント一覧
花粉症治療薬を取り扱う製薬会社のHPでは、室内環境の整備が花粉症予防に大切だと説明されています。花粉は髪や衣服に付着して室内に持ち込まれるので、こまめな床掃除で取り除く必要があります。以下の表で床の素材ごとに掃除のポイントをまとめたので参考にしてください。詳細については下の項で順番に解説します。
■床素材ごとの掃除方法のポイントと使う道具
| 掃除のコツ | 使用する道具 | 関連商品 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フローリング | 掃除機を最初にかけるのはNG。丁寧な水拭きが基本。 | ・雑巾 ・掃除機 |
・EF-モコモップマイクロ | ||||||
| 絨毯 | 掃除機などで繊維内の汚れを取り除く。 | ・コロコロ ・掃除機 |
・オフィスコロコロ ・充電式クリーナ |
||||||
| 畳 | 畳の目にそって水拭きする。 | ・雑巾 ・掃除機 |
・TioTio | ||||||
| フロアタイル | 日々の水拭きだけでOK。汚れたら洗剤等を使用。 | ・雑巾 ・洗剤 ・漂白剤 |
・モップ ・化学モップ |
||||||
| カーペット | 絨毯と同様に繊維内の汚れを取り除く。 | ・コロコロ ・掃除機 |
・ポリシャー ・綿パット |
||||||
床掃除のポイント1:フローリング
フローリング掃除の鉄則は「いきなり掃除機を使わない」ことです。フローリングは絨毯などの様に繊維に汚れが絡みつくことはなく掃除が簡単なイメージがあります。しかし、実際には花粉やハウスダストは舞い上がりやすいというデメリットがあります。ある研究ではラグを敷いたときの約2倍のハウスダストが舞うと報告されているので、掃除機の排気によって空気中に飛散させることは絶対に防ぎましょう。
掃除の手順は濡れた雑巾やフローリングワイパーで木目に沿ってゆっくりと拭くだけで問題ありません。注意点としては雑巾などに汚れが溜まってきたらこまめに洗うことです。また、掃除機を使いたい場合には、雑巾等で拭き終わった後に吸引力を「弱」にして使いましょう。
フローリング掃除に最適なEF-モコモップマイクロ
フローリング掃除のおすすめアイテムが「EF-モコモップマイクロ」というマイクロファイバー素材の水拭き用シートです。このシートはEF-マルチモップ、いわゆるフローリングワイパーに装着して使用できます。洗剤を使わずとも砂・ホコリ皮脂・油汚れを効果的にかき落とすことが可能で、その上、洗って何度でも使えます。さらに繊維の長さにコントラストをつけた構造なので、抵抗が少なく楽に拭き取れます。なお、市販のフローリングワイパーに装着する際は事前にヘッドのサイズがあっているかを確認してください。
床掃除のポイント2:絨毯
布製品には花粉が付着しやすく、繊維の奥深くに入り込むこともあります。そのため絨毯の汚れについては、カーペットクリーナー(コロコロ)か掃除機を使って、強力にかき出すようにしましょう。掃除の時間帯についてはフローリングと同じく朝一番が最適です。
強接着テープで花粉を除去するオフィスコロコロ
強い粘着力を持つコロコロです。「強粘着スペア」という強接着テープを使うことで、カーペットの奥の花粉やダニを取り除くことができます。ただし、絹や20mm以上の毛足の長い絨毯には適していないので、使用には注意してください。
ハイパワーかつ軽量の充電式クリーナ
コードレスのハンディクリーナ(掃除機)です。絨毯の掃除に適したノズルもあるので、必要に応じてご使用ください。また、高輝度LEDライトがついており、家具の下など暗い場所でも快適に掃除できます。軽く、充電も早く、さらには紙パックが不要なので非常に使い勝手の良い掃除機です。
※関連ページ:テラモト「カタログ(コロコロ:p392~393)(充電式クリーナ:p454~455)」
床掃除のポイント3:畳
畳の目の隙間には花粉やダニが入り込んでいます。掃除機で吸引するか、雑巾で丁寧に拭いてください。雑巾は濡らして固く絞ったものを使うか、霧吹きで軽く濡らして使用するのが良いでしょう。いずれにしても畳の目に沿って拭き取ります。
畳以外にもオールマイティに使えるFX制菌クロス(TioTio)
ここで紹介するTioTioというお掃除クロスは、畳に限らずガラス、テーブルを拭くのに活用できます。特に今は新型コロナウイルスが蔓延しているので、ドアノブ、スイッチ類、ステンレス、飛沫防止パネルなど、ウイルスが付着しがちな場所で使用するのもおすすめです。商品の特長としては以下の3点があります。
1.制菌&抗菌防臭
TioTio加工という技術により、クロス上の細菌の増殖を抑制。また、生乾きの臭いの原因成分を分解する。
2.抜群の汚れ除去性能
超極細繊維から成っており、目に見えない凸凹に入り込み、小さな汚れやホコリを除去できる。
3.強力な速乾性
本体には無数の穴が開いており、洗濯後の渇きが早い。
※関連ページ:テラモト「カタログp362~363」
床掃除のポイント4:カーペット
カーペット・絨毯・ラグなどはサイズ感や詳細な定義こそ異なるものの、基本的には繊維製の敷物として類似したものです。そのため、先ほど紹介した絨毯と掃除の基本はあまり変わりません。先述したように、朝一番にコロコロや掃除機で繊維に絡みついた花粉を取り除くと良いでしょう。ただし、オフィスなどのカーペットは泥や土で汚れるので、家庭用とは少し事情が異なります。以下では汚れたカーペットを洗浄できる商品を紹介します。
カーペットのシミにはポリシャー
弊社では床磨きに便利なポリシャーを販売しています。ポリシャーと言えばタイル磨きのイメージがあるかもしれませんが、先端パーツを取り換えられるので、カーペットの洗浄も可能です。具体的には「綿パット」というパーツがカーペット洗浄に対応した商品です。ここではカーペットに焦点を当てていますが、床の種類や用途に合わせて数種類のパーツを取り揃えていますので、ご興味あればカタログをご覧ください。
※関連ページ:テラモト「カタログp458~459」
花粉症対策になるカーペットの選び方
花粉症の方にとって、カーペット選びは住環境の快適さを大きく左右する重大なポイントです。繊維の中に花粉が入り込みやすいカーペットは、選び方を間違えるとアレルゲンの温床になりかねません。そこで重要になるのが、花粉の付着を抑え、掃除しやすい素材と構造のカーペットを選ぶことです。
おすすめなのは、防ダニ・抗アレルゲン加工が施されたカーペットです。これらの製品は、繊維に特殊な加工が施されており、花粉やダニの死骸、フンなどのアレルゲンの働きを抑える効果があります。日本アトピー協会の推薦品マークがついている商品もあり、信頼性の高い選択が可能です。
また、毛足の短いループパイルタイプのカーペットも、花粉症対策に適しています。毛足が長いシャギータイプやフカフカのラグは、繊維の奥まで花粉が入り込み、掃除機でも取り切れない場合があるので注意。一方、ループパイルは表面が平らで掃除機がかけやすく、花粉やホコリを溜め込みにくい構造です。掃除のしやすさという点で大きなメリットがあります。
さらに注目したいのが、洗えるカーペットです。最近では家庭用洗濯機で洗える薄型のラグやカーペットが多数登場しており、花粉の季節には週に一度のペースで洗濯すれば、常に清潔な状態を保つことができます。速乾性の高い素材であれば、天気の良い日に朝洗って午後には再び使用できるものもあります。
素材としては、ナイロンやポリエステルなどの合成繊維が理想的です。天然繊維(ウールなど)は肌触りは良いものの、花粉やハウスダストが繊維の奥に入り込みやすく、頻繁なメンテナンスが求められます。合成繊維は表面が滑らかで、花粉が絡みにくく、取り除きやすいため、花粉症対策に適切です。
最後に、裏面に滑り止め加工があるかどうかも重要なポイントです。ズレたり折れたりするカーペットは掃除の効率を下げるだけでなく、汚れの再付着を招くため、固定されている構造のほうが花粉除去には有利です。
このように、素材・構造・機能性に注目してカーペットを選ぶことで、花粉症の症状を軽減しやすくなります。毎日の掃除だけでなく、インテリア選びも花粉症対策の一環として見直してみましょう。
季節の変わり目には業者の力を借りるのもおすすめ
花粉の季節や気温の変化が大きい季節の変わり目には、プロのハウスクリーニング業者に掃除を依頼するのも有効な手段です。特に花粉の飛散がピークを迎える春先や、エアコンを使い始める初夏・晩秋などは、家庭では取り切れない汚れやアレルゲンが蓄積しやすい時期です。
業者は専用の機材や薬剤を使用して、カーペットやソファ、エアコン内部まで徹底的に清掃してくれます。こうした作業は家庭ではなかなか行き届かないため、季節ごとに一度プロの手を借りることで、住環境の衛生を維持しやすくなります。
特に花粉症やアレルギーが気になる方には、アレルゲンの除去を専門とする業者の利用がおすすめです。日頃の掃除とプロの力を上手に使い分け、より快適で清潔な住まいを保ちましょう。
床の素材によって床掃除の方法は変わる
皆さんは床の素材によって床掃除の仕方を変えているでしょうか。いつの間にか家中が花粉だらけ、ということも考えられるので、できる限り正しい道具・手順で掃除しましょう。どうしても難しい場合は「お掃除ロボット」に頼るのも良いかもしれません。水拭きができるロボットを朝一番に起動するようセットするだけで、床の花粉を効果的に除去できます。他にも汚れ切った絨毯類を業者に頼んでクリーニングしてもらうのも楽に掃除するための選択肢です。自分に合った方法で清潔な我が家を手に入れましょう。